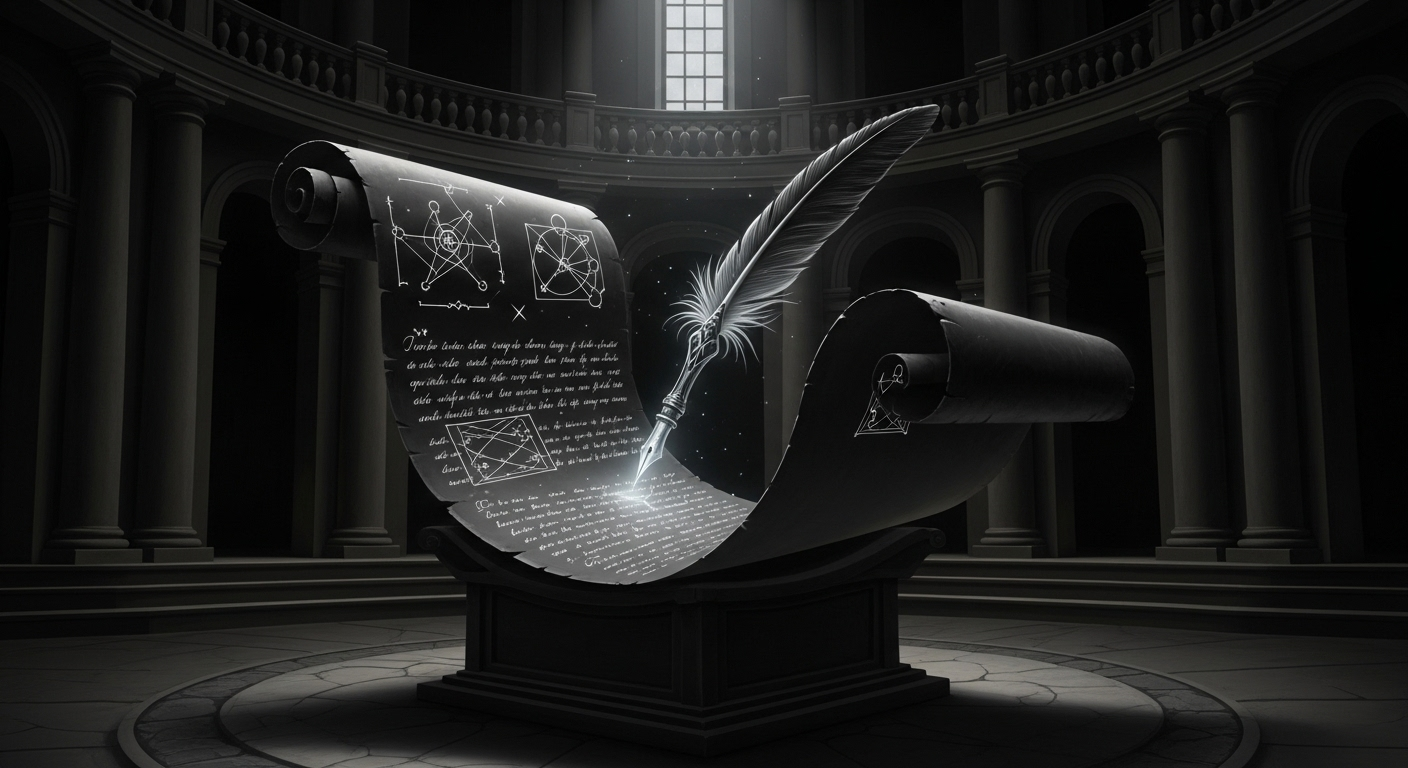提案資料AIベルテくんの解説と、作れる資料の見本、使うコツをお届けします。
こちらは先行販売での公開版です。すでに実用できる精度にはなっていますが、テストがまだ十分でないため、使ってみて気になる部分などはぜひご意見・ご要望をお寄せください。
今後も更新を重ね、問題やバグなどでには可能な限り対応し、よりブラッシュアップを重ねていきたいと思っています。
なお、これ以降、更新した部分は適宜メルマガでご連絡させていただきます。
動画解説
提案資料作成セミナー統合サマリー(AI活用 × ロジック設計 × Gamma運用)
目的
- AIを活用して短時間で訴求力の高い提案資料を作成できるようにする
- ツール依存ではなく、資料設計のロジック(理論)を理解し主体的に使いこなす
- 有料AIツール「資料作成ベルテくん」にロジックを学習させ、台本・骨子・順序を再現可能にする
- Gamma(ガンマ)でのスライド化・共有・エクスポートを短時間で完了させる
全体フロー
- 情報準備(商品・ターゲット・課題・ベネフィット・市場)
- ベルテくん/ChatGPTで原稿・骨子生成(1スライド1メッセージ化)
- 訴求順序ロジックに沿って構成化(ベネフィット→価格→CTAまで)
- Gammaでアウトライン取り込み→レイアウト調整→画像・図表設定
- 価格・比較・オファー・CTAを仕上げ、共有・PDF/PPT出力
素材準備(コア情報と姿勢)
- 商品/サービス名、ターゲット属性、悩み・課題(初期ヒアリングの明確化)
- ベネフィット(購入後の理想の未来)、ハウ(機能・便利さ:優先度は低)
- マーケット情報(トレンド・情勢・データ・背景)
- なぜ今必要か、誰に購入理由が成立するか、市場俯瞰
- 未充足情報は顧客ヒアリングで深掘り→対話で仮説検証し充足
タイトル設計の原則
- ターゲット明示:個別名指し(◯◯様専用)、属性明記(業種など)
- ベネフィット先行:手段名を避け、理想の未来で引き付ける
- 物や手段ではなく便益を前面に提示
タイトル例:◯◯様専用|製造業のための売上・集客を1.5倍にするウェブ戦略提案
提案資料の訴求順序(核ロジック)
- ベネフィット提示:到達可能な理想の未来を冒頭で明確化
- 悩み・課題の指摘:ヒアリング内容を箇条書きで認識合わせ
- エビデンス:ビフォーアフター、実績数字、口コミ、モニター、インタビュー
- 強い証拠は前方配置(自己紹介より先)で集中と信頼を獲得
- 簡潔な自己紹介:実績・専門性を短く(過度な自分語りは回避)
- 解決策提示:なぜ成果が出せるかの構造と根拠を簡潔に(ノウハウ詳細は最小限)
- 他の解決策比較:競合・他手段の並列化→目の前の顧客に最適解を示す
- 最悪の未来の提示:放置リスクを具体例で明示(今動く動機形成)
- 価格提示(松竹梅):定価→アンカー→期間限定オファーで「どれにするか」に転換
- クロージング:伴走姿勢を明言し、CTA(連絡先)へ直結
エビデンス重視のスタンス
- 最重要:ビフォーアフター、実績数字、口コミ、モニターインタビュー
- 補助的:成分・専門用語・難解理論(権威付け)
- 強いエビデンスがあれば詳細ノウハウ説明は不要
- 例:3カ月で月収100万円到達の事例、15年以上の業界経験、美容健康は変化写真・継続データが有効
ツール活用方針
- 提案資料作成AIベルテくん(GPTs)
- 訴求順序ロジックに沿った台本・骨子・エビデンス配置を自動補助
- 会話型ヒアリングで必要要素を収集(サービス・ターゲット・課題・成果目標・競合・予算)
- ガンマ最適アウトライン、1スライド1メッセージ、キャッチコピー最適化
- 誠実性重視(過度な誇張は禁止)、ユーザーが自作可能なテンプレ提供
- Gamma(ガンマ)
- 生成AIによるレイアウト自動化、画像・アイコン・図表生成
- Webページ/プレゼン両対応、PDF/PPT/Googleスライド/PNGエクスポート
- 無料枠はロゴ表示あり/10枚制限、課金で拡張
Gamma運用の実務要点
- スライド比率:16:9推奨(プレゼン標準)
- テーマ:プロフェッショナル系+後編集で可読性調整(色・フォント)
- コンテンツ自動配置:ボックス化、アイコン挿入、背景画像設定
- レイアウト切替:連結ボックス/サイドライン/リーフ型などで即変更
- 画像・コスト:背景生成はクレジット消費→ImageFX等で外部生成しアップロードが合理的
- 図表機能:フローチャート→タイムライン化、グラフ(棒・折れ線・円等)は項目を手動再配置
- 共有・出力:リンク共有、PDF/PPT/Googleスライドで即納品
- ランニングコスト:有料(月約1,500円)でロゴ非表示、無料でも実務支障は小
提案資料の思想(無形商材に効く設計)
- デザイン過剰投資より「わかりやすい中身」と伝達性を優先
- 白地+黒文字でも、訴求順序とエビデンスがあれば十分に刺さる
- 画像は物販では効果的、無形訴求では必須ではない
価格・訴求・保証の設計
- 価格は松竹梅+アンカリング+期間限定オファーで意思決定を促進
- 市場比較での価格妥当性を示し、返金保証は障壁低減に有効
- 例:最低3カ月、成果ゼロ時返金、納品記事は返却(資産保全)
ケース適用例(haku-bi:陶器ブランド)
- 企画タイトル案:ハクビ様向け 泣ける陶器ストーリーで認知拡大&ファン育成するコンテンツマーケティング施策
- 目的:認知拡大/売上ライン拡大/ブランド価値向上/ファン育成
- 切り口:物語性・手触り・日常性に合致する「泣けるストーリー」で共感獲得
- 構成(例):
- タイトル(個別化+便益)
- 施策主旨(物語×認知・売上・ファン化の同時実現)
- 市場課題(広告費高騰・価格競争・差別化難)
- 適合理由(潜在層×共感設計)
- 解決策(ブログ/note展開+SEO設計)
- 他手段比較(広告・SNS・コンテンツの資産性比較)
- メリット(依存低減・信頼向上・リピート・模倣困難)
- 実施フロー(初月→3カ月→半年のロードマップ)
- 予算と価値(例:月10本12万円/20本20万円、広告換算50〜100万円)
- クロージング(短期消耗戦ではなく長期基盤づくり)
- KPI/ロードマップ:
- 初月:記事公開、基礎SEO、連載導入
- 3カ月:検索流入の兆候、滞在・回遊改善
- 6カ月:コンテンツ起点のCV増、リピート・会員化・指名検索増
- リスク認識:半年の売上伸長はやや楽観(業界・競合・ドメイン体力依存)→資産性で補完
実践上の注意・推奨
- タイトルと序盤で「あなた専用性」と「理想の未来」を強調
- 課題指摘で認識合わせ→強エビデンスで信頼獲得→解決策は簡潔
- 比較は角を立てず最適解へ誘導(探索労力を削減)
- リスク提示は具体例で「今動く」動機を形成
- 価格は選択フレーミング化(買う/買わない→どれにするか)
- 強圧的クロージングは禁物。最後にCTAと連絡導線を明記
ガンマ操作・品質最適化のチェック
- 16:9比率、プロ系テーマ、可読性検証
- 1スライド1メッセージ徹底、必須スライド(自己紹介/比較/価格/CTA)漏れ防止
- 背景画像は透過・オーバーレイで可読性確保、強調色でメリハリ
- フローチャート→タイムライン、グラフは見やすく手動再配置
- 無料ロゴの許容/有料化の判断、クレジット消費の最適化(外部画像併用)
まとめ(結論)
- 成約率の中核ロジックは「ベネフィット→課題→証拠→信頼→解決策→比較→リスク→価格→伴走→CTA」
- タイトル・冒頭設計で9割が決まる。個別化と理想未来の明示が鍵
- エビデンスの量と質が最重要。ノウハウ詳細は補助
- 価格は松竹梅+アンカー+期間限定で意思決定を加速
- AIは理論理解のうえで使うことで真価を発揮。ベルテ君×Gammaで30〜60分の高速仕上げが可能
実行チェックリスト
理解できたかを下記の項目ごとにチェックしてみてください。
☑️ 素材収集(商品・ターゲット・課題・ベネフィット・市場データ)
☑️ 初期ヒアリング要約(課題の箇条書き化)と認識合わせ文案
☑️ 強エビデンス(BA/実績/口コミ/モニター/数字)の収集・配置計画
☑️ タイトル個別化案(◯◯様専用+属性+理想未来)
☑️ 競合・他手段の比較表(属性別スクリーニング)
☑️ リスク提示(放置の最悪シナリオ)原稿
☑️ 価格プラン(松竹梅)+アンカー/限定オファー条件
☑️ 伴走メッセージとCTA(連絡先)整備
☑️ ベルテ君にロジック・テンプレ学習→トークスクリプト生成
☑️ Gammaでアウトライン反映→スライド化(16:9/プロテーマ)
☑️ 画像プロンプト設計(ポジ/ネガ)→外部生成併用でコスト最適化
☑️ KPIとロードマップ確定(初月・3カ月・6カ月)
☑️ 料金根拠(広告換算・資産性)の明文化
☑️ 無料クレジット・ロゴ有無の運用判断(必要に応じ課金)
☑️ 返金保証文言テンプレ(任意)とリスク表記の適正化
☑️ 当日進行台本(圧迫しない意思決定促進フレーズ)準備
動画で使ったマインドマップ
復習や内容の確認にお使いください。
※このマインドマップは、下記のXmindというツールで作られています。無料でDLできます。
https://jp.xmind.net/download/xmind8
「提案資料作成AIベルテくん」ツール本体
プレゼン資料作成AI「Gamma」
Gammaはここから登録すると、僕とユーザーさんに200クレジット入るようなので、良かったら下記リンクから登録してもらえると嬉しいです。
Gammaで制作した資料サンプル
この資料に沿った提案トーク台本
資料タイトル:
「泣ける陶器ストーリー」で顧客を育てる長期戦略
(Hakubi 提案)
🎤 スライド1:タイトル「泣ける陶器ストーリー」で顧客を育てる長期戦略
ねらい:導入で共感を引き出す
🗣️ 話し出し:
「こんにちは。今日は、“泣ける陶器ストーリー”というちょっと変わったテーマでお話しします。
最近、お客さまとの関係づくり、難しくなっていませんか?」
📖 説明ポイント:
「この資料では、“いま買う”お客様だけでなく、“そのうち買う”方とのつながりを育てていく戦略をお伝えします。
陶器のような思い入れの強い商品ほど、物語があるとファンが長く残る傾向があります。
実際に、SNSや店舗で“背景に心が動く話”があるブランドほど、リピート率が20〜30%高いというデータもあります。」
💬 会話フック:
「御社のお客さまも、“なんとなく好き”で来てくれている方、多くないですか?」
🎤 スライド2:市場の現状と課題
ねらい:現状の痛みを共有し、問題意識を合わせる
🗣️ 話し出し:
「まずは、いまの市場状況を一緒に見てみましょう。」
📖 説明ポイント:
「陶器・雑貨業界ではSNSの競争が激化していて、“見栄え”だけで選ばれる傾向が強まっています。
広告費をかけてもすぐに埋もれ、結局フォロワーが増えても売上につながりにくいケースが多いです。
さらに、“値引きや限定キャンペーン”でしか反応しない層が増え、利益率が下がっています。
つまり、短期の販促依存から抜け出せない構造ができているんです。」
💬 会話フック:
「御社でも、最近“インスタ投稿の手応えが減った”という実感、ありませんか?」
🎤 スライド3:なぜ「そのうち客」に注目するのか
ねらい:「今すぐ客」依存の危うさを気づかせる
🗣️ 話し出し:
「ここで大事なのが、“そのうち買うかも”というお客さまの存在です。」
📖 説明ポイント:
「多くの店舗では“今すぐ買う人”だけを追いかけています。
でも実際には、将来的に買う可能性のある“そのうち客”が全体の約7割を占めると言われています。
この層がブランドを忘れないように、日常的に“好き”を育てていくことが、長期の売上安定につながります。」
💬 会話フック:
「たとえば、お店の常連さんで“毎回は買わないけど、ずっと見てくれている人”、いませんか?」
🎤 スライド4:解決策「泣ける陶器ストーリー」コンテンツマーケティング
ねらい:解決策を具体的に提示する
🗣️ 話し出し:
「では、どうやって“そのうち客”をファンに育てるのか?
それが、“泣ける陶器ストーリー”という考え方です。」
📖 説明ポイント:
「たとえば、作家さんの制作背景や、器にまつわる“想い出エピソード”を発信する。
“買う理由”よりも、“共感する理由”を伝えることで、SNS上でファンが自然に拡散してくれます。
1話完結のストーリー形式を続けることで、“読むだけでも心が動くブランド”として認知されていきます。」
💬 会話フック:
「御社の商品で、“背景を語れるエピソード”って、どんなものがありますか?」
🎤 スライド5:効果の実績
ねらい:信頼と導入後のイメージを具体化する
🗣️ 話し出し:
「実際に、このアプローチを導入した店舗ではこんな変化が出ています。」
📖 説明ポイント:
「Instagramの保存数が約3倍、投稿あたりの滞在時間が1.8倍に増加。
さらに、ストーリー発信を続けた3か月後に、DM経由での問い合わせ率が約25%アップしました。
直接の購入より、“心に残る体験”が口コミの原動力になるんです。」
💬 会話フック:
「SNS投稿を“売るための宣伝”ではなく、“読むと気持ちが動く投稿”に変えるとしたら、何を伝えたいですか?」
🎤 スライド6:実施メリット
ねらい:導入する価値を再確認させる
🗣️ 話し出し:
「この取り組みで得られるメリットを整理しますね。」
📖 説明ポイント:
「まず、共感ベースの投稿が増えると、ブランド好感度が上がります。
次に、ストーリーが積み重なることで、“世界観のあるお店”として差別化できます。
結果的に、リピート購入率が上がり、単価も上がる傾向があります。」
💬 会話フック:
「“お店の世界観を言葉で伝える”こと、今どれくらい意識されていますか?」
🎤 スライド7:実施フロー
ねらい:導入のハードルを下げる
🗣️ 話し出し:
「進め方はとてもシンプルです。」
📖 説明ポイント:
「まず、ヒアリングで“お店や商品に込めた想い”を聞かせていただきます。
次に、ストーリー構成と撮影計画を作成。
その後、月2本ペースで投稿や記事として配信します。
最初の1か月でプロトタイプを確認し、反応を見ながら調整していきます。」
💬 会話フック:
「どのくらいの頻度なら、無理なく発信できそうですか?」
🎤 スライド8:予算と費用感
ねらい:価格への不安を先回りして解消する
🗣️ 話し出し:
「費用の目安はこんな形です。」
📖 説明ポイント:
「単発のストーリー制作は12万円〜、月次運用は20万円〜。
写真や動画撮影込みで、50〜100万円の範囲でご提案できます。
初期は少額スタートも可能なので、まずは1本試してみるのがオススメです。」
💬 会話フック:
「まず1本だけ試して、反応を見てみる、という形はいかがですか?」
🎤 スライド9:まとめ・次の一歩
ねらい:行動喚起と安心感の提示
🗣️ 話し出し:
「最後にまとめです。」
📖 説明ポイント:
「“見栄えで選ばれる時代”から、“共感で選ばれる時代”へ。
ストーリーは、今後のブランドの資産になります。
Hakubiでは、想いを言葉と映像にして、“共感で売れる仕組み”を一緒につくります。」
💬 会話フック:
「まずは、御社の商品でどんなストーリーが描けそうか、10分だけ一緒にアイデア出してみませんか?」
WEBデザイナーのための、ゼロからの提案資料の作り方
(アップグレード2.0版)

過去にリリースした提案資料作成コンテンツを、2025年版に大幅加筆修正してリビルドしています。
【5万の案件を20万にする、極悪非道に見えて実は品行方正な方法】
こんにちは、イチです。
上で公開した動画「AIを活用した提案資料の作り方」は、もうご覧いただけたでしょうか。
見ていなかったら、ぜひそちらをご視聴後にこちらを読んでください。
AI、特に僕が作ったツールである「提案資料作成AIベルテくん」を使えば、まるで電子レンジのように、ボタン一つで高品質な提案資料の原稿が出力できてしまいます。
そのスピード感とクオリティに、驚かれた方も多いかもしれません。
しかし、AIはあくまで”強力な武器”に過ぎません。
その武器の裏側にある「なぜそう動いているのか」というロジックを理解していなければ、あなたもいずれ「AIに使われる側」になってしまいます。
そこで今回は、動画ではお見せした「作り方(How)」のさらに奥深くにある、「なぜ、その作り方でなければならないのか(Why)」という思考法や理論について、1ミリも隠さず、全てあなたに提供したいと思います。
この理論を完全に理解し、自分のものとしたとき、あなたは5万円で作ってくれと言われた案件を20万円にすることも、20万円の案件を100万円にすることもできるようになります。
しかも押し売りではなく、お客様に心の底から喜ばれ、「ぜひ、それでお願いしたい」と言われながら。
これから解説する各章は、旧来から僕が実践してきた提案資料作成のノウハウを、AI時代に合わせて完全にリファインしたものです。
動画で見たテクニックの根拠を理解することで、あなたはAIツールを真に使いこなし、誰にも真似できない提案力を手に入れることができるでしょう。
0.AIに入力する「魂」を創る:提案の本質はヒアリングにあり
動画では、AIに商品情報などを入力して、すぐに原稿を作成する流れをお見せしました。
しかし、あの入力情報そのものにこそ、提案の成否を分ける「魂」が宿っています。そして、その魂は、お客様との深い対話、つまりヒアリングによってしか創り出すことはできません。
ヒアリングでは、WhatではなくWhyを問う
多くのデザイナーは、ヒアリングでお客様の「どんなものがほしいのか(What)」を聞くことに終始してしまいます。
これは「相手の望んだものを提供する」というだけで、相手の予算を超える仕事はできません。
本当に大切なのは、そこではありません。
「なぜ、それを作りたいのか(Why)」を、お客様自身も気づいていないレベルまで深掘りしていくこと。
ここが、提案全体の質を決定づける、最も重要なプロセスです。
お客様の事業や、その先にあるKPI(中期目標)/KGI(最終目標)を深く理解する。
これができると、お客様が本当に欲しい未来に到達するための、「全く新しい切り口」を僕たちから提案できるようになります。
分かりづらいと思いますので、例を出しましょう。
お客様があなたに「チラシを5万円で作りたい」と言っているとします。目的を聞くと「集客」だと答えます。この時、「どんなデザインにしますか?」と聞くのはWhatのヒアリングです。
そうではなく、「なぜ、集客方法としてチラシをお考えなのですか?」とWhyを問うてみてください。
多くの場合、お客様はその手段しか思いついていないだけなのです。
そこで、あなたがこう提案します。
「チラシは素晴らしいきっかけになります。
そのチラシにQRコードを埋め込み、LINE公式アカウントに登録してもらうのはどうでしょう?
興味を持ってくれた人をリスト化し、LINEで有益な情報を届け、最終的にLP(ランディングページ)で商品をご案内する。
こうした一連の『集客の仕組み』を構築すれば、チラシを1度配っただけで、繰り返しそのお客様に案内を送ることができるようになります」
お客様は、ただチラシを配るよりもずっと成功確度の高そうなこの施策にワクワクするはずです。そして、この仕組み全体をパッケージ化して、20万円でオファーするのです。
お客様は「ぜひお願いしたい」と言ってくれるでしょう。
案件が来たら、「何を作るか」だけに思考を留めず、「なぜそれがほしいのか」をヒアリングし、「お客様が本当に欲しい未来」を見極めてください。
そして、その目的を叶える、もっと良い手段を考えてみる。
この思考プロセスこそが、あなたの提案の価値を何倍にも高める源泉になります。
そしてこの思考をするうえでは、僕の提案ナレッジのすべてをインストールした「提案資料AIベルテくん」を壁打ち相手にしてもいいでしょう。
提案を思考するためには、手段を知る
このためには、導線設計の知識、LINEステップ運用の知識、HP、LP、ECなどの多岐にわたる「問題解決手段」を広く知っていることが重要です。LPだけとか、LINE運用だけとか、ひとつのプロダクトしか提供できないと、この切り口で提案していけないので、自分の単価を上げるチャンスを逃すことになります。
「すべてを自分で作れる必要」は一切ありません。
一部を外注してもいいのです。
ただ、「問題解決手段」は、少しでも多く、自分の知識として持っておくこと。
それがあなたの単価を5倍にも10倍にも上げるあなたの武器、「提案力」になります。
クライアントのリテラシーを見定める
もう一つ、ヒアリングで大切なことがあります。
それは、提案する相手のITリテラシーをさりげなく見定めておくことです。
例えば「インターネットを普段全く使わない方」にホームページの話をするのと、「普段からネットを使いこなしている方」にするのとでは、使うべき言葉が全く異なります。
「ドメイン」や「サーバー」という言葉を知らない方には、まずそれが何なのか、というところから丁寧に解説する必要があります。最初の会話の中で「ランニングコストとしてドメイン代などがかかりますが、こちらについてはご存知ですか?」と、そっと聞いてみればいいのです。「知らない」と言われたら、「では、そこから丁寧に解説させていただきますね」と続ければ、相手も安心して話を聞いてくれます。
相手の知識レベルを見誤ると、せっかく良い提案をしても「難しくてよく分からなかった」という残念な結果になってしまいます。相手に合わせた言葉を選ぶ。これも提案における大切な思いやりです。
このセクションのまとめ
- AIに的確な指示を出すための「魂」は、お客様への深いヒアリングから生まれる。
- 「Why(なぜ)」を問い、顧客の真の目的を掴み、幅広い「問題解決手段」の知識を武器により良い提案をすること。
- 提案の言葉は、お客様のリテラシーレベルに合わせて調整し、確実に理解してもらう努力をせよ。
提案資料を作成する前の、初回打ち合わせで聞くべきヒアリング項目
一般的なヒアリングシートを埋めてもらうのでもいいが、一応参考までに、聞くべき項目を書き出しておきます。
提案資料の良し悪しは、デザインでも構成でもなく、最初の「ヒアリングの深さ」で決まります。
つまり、AIに入力する前の素材収集の段階で、勝負はすでに八割方決まっているのです。
1. 現状把握(Before)
まず、現状を正確に把握することが大切です。
いきなり「どうしたいですか?」と聞くのではなく、今の状況を言語化してもらいましょう。
・現在、どのような集客・販売経路でお客様を獲得していますか?
・今の施策でうまくいっている点、うまくいっていない点はどこですか?
・平均的な売上・客単価・成約率はどのくらいですか?
・これまでにどんな改善策を試されましたか?
この質問によって、お客様の中にある「暗黙の課題」が浮き彫りになります。
ここを雑に聞き流してしまうと、AIがどんなに賢くてもズレた提案になってしまいます。
2. 目的と理想の未来(After)
ここからが本番です。
この質問で、提案の方向性が決まります。
・今回、最終的にどんな状態を目指したいですか?
・もしこの施策が成功したら、どんな未来を実現したいですか?
・その未来を実現することで、どんな良い変化が起きそうですか?(例:時間・お金・人間関係・ブランド)
・数字で言うと、どのくらいの成果を期待していますか?
このとき、「売上を上げたい」などの表面的な答えが返ってきても、そこで終わらせないことが重要です。
「なぜその売上を目指すのか」「なぜ今その未来を叶えたいのか」まで掘り下げていきます。
これが、AIベルテくんに入力する「Benefit(理想の未来)」の根幹になります。
3. 課題・悩み・障壁(Problem)
次に、現状のボトルネックを明確にしていきます。
・今、一番の課題は何だと思いますか?
・その課題はいつから続いていますか?
・それを放置すると、今後どんなリスクがありますか?
・ご自身で解決しようとして難しかった部分はどこですか?
この質問群は、「お客様自身の言葉」で問題を語ってもらうためのものです。
提案資料では、このフレーズをそのまま引用すると非常に効果的です。
お客様が「自分の言葉で書かれた資料」を見ると、「自分のために作られた」と感じてくれるからです。
4. 競合・市場・トレンド(Market
AIに強い資料を作るためには、市場データが欠かせません。
・競合や同業で「うまくいっている」と感じる企業・店舗はありますか?
・最近、業界全体で変化を感じる点はありますか?
・ターゲット顧客層の変化やニーズの変化を感じますか?
・他社との違い(差別化ポイント)はどこだと思いますか?
ここで得た情報は、AIに渡す「Market(市場情報)」として入力します。
数字やデータがあれば理想的ですが、定性的な印象でも構いません。
Gammaでスライド化するとき、この部分が「市場理解」のスライドに変わります。
5. ベネフィット(Benefit)
提案資料の冒頭で「この施策で得られる理想の未来」を語るための素材です。
・あなたの商品・サービスを使ったお客様は、どんな良い変化を得ていますか?
・それをもっと多くの人に届けられたら、どんな影響がありそうですか?
・顧客の喜びの声や口コミの中で、印象的な言葉はありますか?
・競合ではなくあなたを選んだお客様の理由は何だと思いますか?
この質問から導き出した「感情的な成果」は、AIベルテくんに入力すると
タイトル案やキャッチコピーに反映されます。
6. 手段・仕組み(How)
AIが「構成」を組み立てるときに必要な素材です。
・今回の提案に使えそうなツールや媒体はありますか?(LP、LINE、SNS、広告など)
・過去に使って効果があったチャネルはありますか?
・実現に向けて、社内・チームで使えるリソースはどのくらいありますか?
・期間やスケジュールに制約はありますか?
AIは、Howの部分を「手段の羅列」ではなく「仕組み化」として構築します。
そのため、ここでは「何をどう使うか」まで具体的に話しておくと、出力の精度が大きく上がります。
7. ターゲット(Who)
ターゲットの精度が低いと、すべての構成がズレてしまいます。
・誰に一番届けたいですか?
・その人はどんな悩みを持っていますか?
・どんなきっかけで商品・サービスを知ると思いますか?
・理想の顧客を一人だけ挙げるとしたら、どんな人ですか?
この情報が明確だと、AIは「訴求順序」と「共感ストーリー」を的確に組み立てられます。
8. 決裁・行動・CTA(Action)
最後に、クロージングまでの流れを見据えておきます。
・この提案を実施するかどうか、誰が最終的に決めますか?
・提案後、どのくらいの期間で判断されますか?
・決定までに懸念されそうなことはありますか?
・最初のアクションとして、何から始めたいですか?
この情報は、Gammaの最終スライド「次の一歩」や「CTA」に活かせます。
また、提案プレゼン時の台本づくりにも役立ちます。
まとめ
AIベルテくんに指示を出す前に、この8項目をヒアリングして埋めていきましょう。
これが「AIに入力する前の設計図」であり、提案資料の心臓部になります。
AIに渡す素材の精度が、提案の深さを決めます。
つまり、ヒアリング力こそが提案力の正体です。
1.人を動かす「論理」の型:なぜAIはあの順番で文章を創るのか
動画で「ベルテくん」が生成した提案資料の原稿、あの文章の順番には、実は強力な法則が隠されています。それが、人を動かすための最強のフレームワーク「PREP法」です。
AIが自動でやってくれるからといって、この型を知らないままでいるのは非常にもったいない。
このロジックを理解することで、AIの出力を自在に操り、あらゆるコミュニケーションに応用できるようになります。
PREP法を、空でも言えるようにしてください
PREP法とは、以下の4つの頭文字をとったものです。
- Point :結論(主張)
- Reason :理由(結論の理由・根拠)
- Example:具体例(理由を裏付ける事例)
- Point :結論(再度、主張)
これはもう暗記して、いつでも使えるようにしておいてほしい。
提案資料だけでなく、ブログ記事やツイート、上司への報告まで、どんな媒体でも応用が効く、思考のフレームワークです。
①結論:なぜ、最初に「結論」を言うべきなのか
日本人は、回りくどい表現をする民族だと言われます。
日本語の構造も、大切なことが最後に来がちですよね。
例えば、「私は長年溜まりに溜まった感情がついに溢れて、今、どうしようもなくあなたのことが好きだ」という文章。
結論である「好きだ」は、一番最後です。
これ、ビジネスの現場でやるとどうなるでしょう。
相手は「で、要するに君は何を言いたいのかね?」とイライラしてしまいます。
ビジネスにおいて、相手の時間を奪うことはコストです。
いたずらに結論を先延ばしにして良いことは何もありません。
だからこそ、「結論から申し上げます」という一言が、ビジネスコミュニケーションでは非常に大切にされるのです。
最初に「何なのか」を伝えることで、相手のストレスを下げ、その後の話を聞く態勢を整えてもらうことができます。
PREP法を、具体例で完全に理解する
理屈だけでは分かりづらいと思うので、誰もがイメージしやすい「告白」を例に、PREP法の流れを見ていきましょう。
- ①結論(Point)
「あなたのことが好きです」 - ②理由と根拠(Reason)
「なぜなら、あなたはいつも私のことを見てくれていて、細かい変化にも気づいて褒めてくれるから」 - ③具体例(Example)
「例えば、私が髪型を変えたら、その日にすぐ『似合ってるね』って言ってくれたし、私が体調を崩していた時も、すぐに声をかけて気遣ってくれましたよね」 - ④再度結論(Point)
「だから、あなたのことが好きです。私と、付き合ってください」
どうでしょうか。この流れで話を展開されると、とても分かりやすく、気持ちがストレートに伝わってきませんか?
「好きだ」という結論が最初に分かっているので、聞き手は「え、どうして?」と、その後の理由や具体例を前のめりになって聞きたくなるのです。
では、これをビジネス資料に置き換えてみましょう
この「告白」のロジックは、そのまま提案資料に応用できます。
ここでは「姿勢改善ベルト」の案件を、このPREP法に当てはめてみますね。お客様の心の動きにも注目してみてください。
1.結論(Point)
この施策は、御社の課題であったサイトのPVを大きくアップさせ、並行して現在ほぼ発生していないCVR(成約率)を3%程度まで引き上げるものです。
【顧客の心理】
何?本当にそんなことができるなら、是非詳しく聞かせてほしい。
2.理由と根拠(Reason)
ではなぜまずPVが上がるかと言うと、現在はオーガニック検索でしか集客できていない状態に、新たにインスタグラムからの流入ルートを構築するからです。さらに、インスタの投稿では「悩みを抱えている潜在顧客」に解決策を訴求することで、【現在御社の商品を知らない人】にまで認知を広げていけるからです。
【顧客の心理】
なるほど。でも具体的にどんな投稿をするのだろう。
3.具体例(Example)
例えば、御社の姿勢改善ベルトは今、腰痛持ちの人にだけしか訴求していませんが、これを「姿勢が良くなると、異性にも同性にもモテる」という切り口で新たな市場を開拓するのです。
インスタでは、このような投稿を行います。
ーーー
PC作業の時、猫背になってませんか?
猫背になるとお腹が出て、立ち姿も自信がなさそうに見えます。
でも、顎を引き、背筋をぴんと伸ばし、肩を張るだけで、男性も女性も非常に対面の印象が良くなります。
「人にモテる姿勢改善ベルト」を使ってみませんか。
ーーー
このような投稿から、そのターゲットに向けたLPを1枚制作して誘導します。
もちろん、インスタ投稿のご提案や代行、コンサルもさせていただきます。
【顧客の心理】
確かにこれだけ具体的な話なら、新規のユーザーの獲得ができそうだな。
4.再度結論(Point)
以上のような施策で、御社のサイトのPVや成約率は大きく改善することができます。
最初の目標は3%ですが、これを達成した暁には、さらに利益を伸ばしていく次のフェーズのご提案も用意しております。
【顧客の心理】
これがうまく行ったら、次の戦略もあるのか!よし、今回はこの会社にお願いしてみようかな。
いかがでしょうか。
「腰痛に悩んでいる」という既存の訴求軸から、新たな「モテたい」という本能的な欲求に商品のベネフィットをすり替え、新たな市場を力強く開拓するための「強い提案」となりました。
これが、お客様の心を動かし、「欲しい!」と思わせる論理の型なのです。
動画で「ベルテくん」が生成した原稿も、このPREP法をベースに、よりセールスに特化した訴求順序で構成されています。
この型を理解することが、AIを使いこなす第一歩になります。
このセクションのまとめ
- 人を動かす文章の基本構造は「結論→理由→具体例→結論」のPREP法。
- 身近な「告白」の例で型を理解し、それをビジネスの提案に応用することで、説得力は格段に上がる。
- AIが生成する文章の裏側にある論理を理解し、その効果を最大限に引き出すこと。
2.AIを使いこなすための「思考の設計図」:なぜ、今もマインドマップが有効なのか
さて、提案の魂となるヒアリング、そして論理の型であるPREP法を理解した上で、いよいよAI活用の具体的なテクニックに入っていきましょう。
ここでは「マインドマップ」にて、お客様のプロダクトを売るための情報と、思考の整理を行っていきます。
ここで、こんな疑問が浮かぶかもしれません。
「これだけ高性能なAIがあるなら、もう自分で深く考えなくてもいいのでは?」「マインドマップで思考を整理する必要なんて、もうないんじゃないか?」と。
この問いに対する僕の答えは、明確に「NO」です。
AI時代だからこそ、僕たちはマインドマップで思考を整理するスキルを、これまで以上に磨くべきだと考えています。
■マインドマップでお客様からヒアリングした情報を整理する
マインドマップはこれまでも別のコンテンツなどで何度か紹介してるからご存知かもしれませんが、もし知らなければ、下記のソフトがおすすめです。僕はもうずっとこれを使っています。
Xmind
https://jp.xmind.net/download/xmind8
まず最初に今回の資料の名前を書きます。マインドマップの形はロジック図にしましょう。
今回は僕の「食べログ記事」の内容を、プレゼン資料に起こす想定でマインドマップを書きました。
https://ichiblog.biz/teian.pdf
マインドマップを書く時点で、その資料の内容を8割9割決めてしまいます。
デザイン以外はここでFIXする。まずサマリーで大体の流れを書き、次にその項目ごとに伝えるべきことをどんどん細かく掘り下げていく。
参考にして書いてみてください。
AIの性能は、あなたが与える「素材の質」で決まる
まず、何の準備もなく、いきなりAIに雑な指示をしたり、突然PowerPointやCanvaで作り始めるのは、正直おすすめできません。
なぜなら、必ず手戻りが発生して、かえって時間がかかってしまうからです。
僕が最初にやるべきだと考えているのは、マインドマップを使って資料全体の構成、つまり「思考の設計図」を書き上げることです。
想像してみてください。
最高の腕を持つシェフ(AI)がいたとしても、あなたが渡した食材(情報)が古かったり、ごちゃ混ぜの状態だったら、美味しい料理は作れるでしょうか?
AIも同じです。
AIはあなたが与えた素材をもとにしか、思考を組み立てることができません。マインドマップは、AIに最高の素材を渡すための、思考整理ツールなのです。
- 思考の抜け漏れがなくなる
「お客様が本当に手に入れたい未来って、具体的にどんな情景だっけ?」
こうした深掘りを、マインドマップなら視覚的に、抜け漏れなく行うことができます。 - 情報に一貫性が生まれる
マインドマップで提案全体のストーリーを俯瞰しながら考えることで、「冒頭で提示した理想の未来」と「最後のクロージング」が一本の線で繋がり、矛盾のない、説得力のあるメッセージをAIにインプットできます。
この「設計図」さえあれば、AIとの対話もスムーズに進みますし、AIの出力をレビューする際も、判断にブレがなくなります。
AIに思考を丸投げするのではなく、AIを最高のパートナーとして使いこなす。
そのために、まずはマインドマップであなた自身の思考を整理することから始めてみてください。
AIに「最強の訴求順序」で原稿を書せる
こうしてマインドマップで思考の設計図ができたら、いよいよAIの出番です。
動画でお見せした「最強の訴求順序」に沿って、AIに原稿を書かせていきましょう。
これは、PREP法を応用し、お客様の感情を揺さぶり、購買意欲を高めるために最適化された流れです。
- タイトル:「〇〇様へ」と名指しし、「売上倍増のご提案」のようにベネフィットを伝える。
- ベネフィットの提示:手に入る最高の未来を改めて語る。
- 悩みや課題の指摘:「これは自分のための資料だ」と思ってもらう。
- エビデンス(証拠)の提示:ビフォーアフターや成功事例で、一気に信頼を得る。
- 自己紹介:相手が興味を持ってくれたこのタイミングで、あなたが何者かを伝える。
- 解決策の提示:なぜあなたのサービスが有効なのかを簡潔に説明する。
- 他の解決策との比較:他の選択肢を潰し、「あなたにはこれがベスト」だと示す。
- 最悪の未来の提示:行動しないことのリスクを伝え、緊急性を感じさせる。
- 金額の提示:「松竹梅」プランや限定価格で、決断を後押しする。
- 最後のご挨拶:「伴走者」としての想いを伝え、信頼関係を築く。
- 連絡先:すぐに行動に移せるようにする。
このロジックを学習させた「ベルテくん」に、あなたがマインドマップで整理した情報を渡すことで、誰でも簡単に、強力なセールスストーリーを生成できるのです。
「Gamma」で一瞬でビジュアル化する
そして、完成した原稿をプレゼンツール「Gamma」に貼り付ける。動画でご覧いただいた通り、AIが文脈を解釈し、適切なレイアウトやアイコンを自動で配置して、美しいスライド資料をものの数分で生成してくれます。
これは、デザイナーにとって革命的なことです。僕たちは、図形の位置を調整したり、配色に悩んだりする「作業」から解放されます。そして、最も重要な「何を、どう伝えるか」という、提案の本質的な部分に、より多くの時間とエネルギーを注ぐことができるようになるのです。
このセクションのまとめ
- AI時代でも、マインドマップは思考整理の最強ツールである。
- AIに与える「素材の質」を高めるために、まず自分の思考を構造化せよ。
- AIを「パートナー」として使いこなし、その能力を最大限引き出すために、思考の設計図を持て。
3.細部に「神」を宿らせる:AIの出力は最高の「下書き」である
AIは驚くほど高品質な資料を生成してくれます。しかし、忘れないでください。AIの出力は、あくまで最高の「下書き」です。最後に、あなたという人間が手を加えることで、その資料にはじめて「神」が宿り、人の心を動かす力が生まれます。
1スライド、1メッセージ
AIが生成した資料を見直す際に、ぜひ徹底してほしい原則があります。それが「1スライド、1メッセージ」です。
資料作りに慣れていない人は、余白を嫌い、情報を一枚にギュウギュウ詰めにしがちです。「なるべく少ない枚数ですべてを伝える」みたいな、貧乏性が出てしまってる人が多いのです。
官公庁や行政機関のパワポとか、結構すごいですよね。補助金系の資料とか。以前、政府主体のSDGs系のイベント資料を見る機会がありましたが、分かりづらいわ読みづらいわで大変でした(笑)。
とにかく1スライドには1メッセージで完結するようにしましょう。プレゼンする時、別に1枚は2、3秒で終わってもいいのです。極端なことを言えば、中央に一言書かれてるだけのページがあってもいい。そういうスライドはインパクトがあり、プレゼンもわかりやすくなります。
参考までに、デザイン性は全くないですが、非常に勉強になるスライドを紹介しておきます。

テンプレートを選び、磨き上げる
基本的には、動画でお見せしたAIツール「Gamma」が自動で生成してくれるデザインで十分なはずです。スピードを考えれば、これが最も効率的でしょう。
ただ、もしあなたが「もっとデザインにこだわりたい」「特定のブランドイメージに沿った資料を作りたい」と思うのであれば、もちろん他のツールを使う選択肢もあります。
その場合は、CanvaやPowerPoint、Googleスライドなどのテンプレートを活用するのがおすすめです。世の中には、プロが作った美しく、分かりやすいテンプレートが無料でたくさん配布されています。
凝りすぎたデザインは、かえって内容の伝達を阻害します。もし使うのであれば、シンプルで、美しいものを選んでください。そして、そこにAIが生成した原稿と、あなた自身の言葉を流し込んでいくのです。
Gamma以外のツールで作りたい場合、Canvaはおしゃれなテンプレートがたくさんあり、操作も簡単、インストールの必要がないWEBツールのため、Canvaで作るのが一番手軽かもしれません。
Canva
https://www.canva.com/ja_jp/presentations/
ただ、より凝ったスライドやプレゼン資料を作ろうと思うと、僕はPowerPointのテンプレートのほうが充実してると思います。パワポと互換性があるGoogleスライドで作ってもいいでしょう。
Googleスライドのデザインテンプレート配布サイト20選
https://bit.ly/3V3UBct
パワーポイント テーマテンプレート配布サイトまとめ30選
https://bit.ly/420HIBY
「WEBサイト」でテンプレートを検索すれば、そのまま提案資料として使えます。
このセクションのまとめ
- 資料は必ず「1スライド、1メッセージ」の原則を徹底し、情報を詰め込みすぎないこと。
- 基本はGammaで十分。
もしこだわるなら、優れたテンプレートを活用し、人間が最終的な仕上げを行うこと。- AIの出力を最高の「下書き」と捉え、あなた自身の言葉と情熱で魂を吹き込む工程を忘れるな。
結論:手段ではなく、「理想の未来」を売るためにAIを使おう
提案資料の作り方を長々と語ってきましたが、最も大切なことは、何よりも「最終的に得られるメリット/ベネフィット」を最初に出すことです。最初に「それがほしい!!」と思われるのが肝心なのです。
僕たちはつい「ホームページいりませんか?」と「手段」から語りがちです。ホームページは、僕たちWEBデザイナーからすると「目的」に見えがちですが、お客様にとっては紛れもない「手段」に過ぎません。目的は、その先にあります。
だから、目的を、お客様が手に入れる「理想の未来」を、まずは訴求してください。そのためには、お客様のことをじっくりと観察し、その心理を深く深く想像する必要があります。
お客様の「ライフスタイル」まで掘り下げる
以前、こんな質問をいただきました。
「理想の未来は『売上アップ』、得られるメリットは『じっくり客の集客』で良いのでしょうか?」
素晴らしい視点ですが、もっと深く掘り下げることができます。
例えば、飲食店への提案なら、「高単価客の開拓とリピーター化」ひいては「優良顧客に対するLTV(顧客生涯価値)の向上」まで語れます。
LTVが向上すればどうなるか?
絶対数は少なくても、濃いお客様が何度も訪れてくれるようになります。マナーの悪い客やクレーム客の相手をしなくても良くなります。究極的には「完全会員制/予約制の高級店」という未来も描けるかもしれません。
そうなれば、「ブランド店になって、好きな時に休み、好きなお客様だけを相手にした、わがままな店舗運営ができる」という、オーナーの「ライフスタイル」に関わるベネフィットまで提案できるのです。
お客様が本当に欲しいのは、売上という数字の先にある、豊かになった自分の生活や、ストレスのない働き方だったりします。そこまで想像力を働かせ、提示してあげること。
AIは、その思考を助け、形にするための最高の相棒です。しかし、お客様の心に寄り添い、真の課題を発見し、理想のライフスタイルまで含めた未来を共に描くという、最も人間的な営みだけは、決してAIに代替されることはありません。
このスキルを磨いてください。そうすれば、あなたの仕事の価値は上がり続け、お客様から心から感謝されながら、望むだけの対価を手にすることができるようになるでしょう。